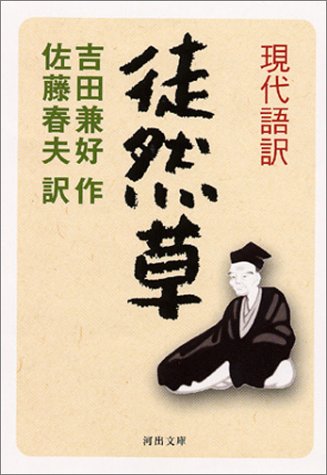今さらながら日本三大随筆のひとつ、『徒然草』河出文庫から出ている佐藤春夫の現代語訳で全文読んでみた。思ったより文章量が多く、予想外に雑多な内容で構成されていたが、翻訳がこなれているせいか楽しく読めた。
昔、教科書で読まされた古典の中で、なぜかこの本だけは記憶に残っている。少なくとも11段「神無月の比…」と52段「仁和寺にある法師…」の2つは、内容までだいたい覚えていた。子どもながらに、何か共感するところがあったのだろう。
エッセイのお手本として、その文体や思想が日本人のメンタリティーに染みついている『徒然草』。どこかで聞いたような「ありがたい話」というのは、たいていこの本に含まれていたりする。700年前の書物なのに、ただならぬ親近感を覚えるのはなぜだろう。
特にオチや結論もない作品なので、個人的に気になった部分を紹介したい。特に中学校・高校の古文練習問題としては、まず取り上げられなさそうな過激な差別的発言、善悪の彼岸を越えた無常観のようなところに興味をもった。
『徒然草』の3つのテーマ
大まかに分類すると、『徒然草』の各段は以下の3つの内容に分けられる。
- 著者がどこかで聞いた話の紹介と、それに対するコメント
- 隠者かくあるべしという、ミニマリストのマニフェスト
- 仏教の無常観に由来する処世術とお説教
まず「栗ばかり食べるので嫁にやれない娘(40段)」とか、「鹿の袋角には脳を蝕む虫がいる(149段)」など、伝え聞いた話を短くメモしているだけ段が結構多い。前後の脈絡もなく、随筆というより漫談・トリヴィアといったエピソードにあふれている。
実はこれだけでもかなりおもしろい。ネット上のスラングで「草」というのは、『徒然草』からきているのではなかろうか。紙面のいたるところにメモして草を生やしてしまった。
ほかの僧や貴族の行動についてコメントしている段では、途中まで「いい話」と見せかけて最後に批判しているパターンも多い。ユーモアや風刺を交えた何気ないコメントにも、独特の皮肉めいた調子が見え隠れする。
さらに「一日の命は万金より重い(93段)」と他人が言った(一見良さげな)話を紹介しながら、結局ポジティブなのかネガティブなのかコメントを避けている段もある。わざわざ書き残してあるからには意味のある逸話だと思うのだが、裏を返せば「しょせん世俗の価値観に過ぎない」と低く見ているようにも思われる。
物のあわれと合理主義
次に目立つのは、在家僧侶として世俗的な身の振り方や、住まいや持ち物の趣味に言及している部分だ。
著者自身は合理的な発想の持ち主らしく、赤舌日(91段)や神無月(202段)といった迷信を批判している。また、上層階級の奢侈浪費をいましめ農業奨励(142段)、庭に野菜や薬草を植える(224段)という堅実な意見も述べている。
公家の自堕落な暮らしを批判し、武士の粗野な行動も「田舎者」とののしる。そして他の僧侶の失敗については辛辣この上ない。隠者としてどの社会階層にも属さず毒を吐いているところが、あらゆる時代に人気を博した理由だろう。
住居については「家の作りやうは、夏をむねとすべし(55段)」の有名な文句がある。また庭のつくりや装飾品、持ち物に関して、派手で高価な唐物(120段)などより、あり合わせの物であっさり済ませるべき(231段)と主張している。
根底にあるのは「もののあはれ(7段)」という美意識だ。「侘び寂び」という言葉は出てこないが似たようなものだろう。未完の美学(82段)や、兼好版の陰影礼賛という一節(191段)もあり、極端なところでは「月や花は目でばかり見るものでない(想像して楽しむ)」という粋なコメント(137段)もある。
ミニマリスト向けまとめ
いかにも現代のミニマリストに好まれそうな美文も多い。たとえば以下のあたりなど。
卑しくも見苦しいもの。身のまわりに日用品の多いこと。硯に筆が多くはいっていること、持仏堂に仏が多いの、前栽に石や植木類が多いの(72段)
古風に、おおおげさでない高価にすぎぬもので、品質のすぐれたのが好ましいのである(81段)
仏道を心がけている者は味噌桶一つも持たないのがよろしい。持経でも御本尊様にしても好いものを持つのは、つまらぬことである。(98段)
毎日欠くべからざるものはなくてはなるまい。それ以外のものは、なに一つ持たないでいたいものである。(140段)
ほかにも「衣食住と薬、これだけ質素に足りれば十分(123段)」など、いたるところでなりふり構わない著者の趣味が披露されている。端的に言うと「わざとらしいのはよくない」というポリシーで、これは後述の「無為自然」という理想に由来している。
バランス感覚
別に「余計なものを持たない(執着しない)」というのは吉田兼好のオリジナルでもなく、仏教全般にみられる基本方針だ。しかし文中から住む家と多少の財産があり、そこまで極端に困窮してない暮らしぶりがうかがえる。何となく『方丈記』の庵のような、シンプルだが上等なものに囲まれて暮らしている風景をイメージできる。
一方で「ことわりたいような様子をしながらも酒も飲めるというようなのが、男としてはいい(1段)」とか、「万事に傑出していても、恋愛の趣を解しない男は物足りない(3段)」という人物評価の出てくるあたり、著者自身は「素っ気なさすぎてもつまらない」と考えているようである。
物に執着しないとはいえ、田舎臭いのは嫌い。そのうえ「古風に、おおおげさでない高価にすぎぬもので、品質のすぐれたのが好ましいのである(81段)」という懐古趣味で本物志向という一面もうかがえる。住まいや道具にこだわらないそぶりを見せて、実はそれなりに洒落者だったのかもしれない。
老子の影響
世渡りの方法としては、高位高官を求めずさっさと隠居するのをよしとしている(吉田兼好は30歳前後で出家)。特に老人が若い人の間に交じって張り切るのはみっともないとか(113段)、調子に乗って失敗した話をこき下ろすパターンが多い。このあたりは中国の古典『老子』の影響が大きいと思う。
徒然草は歴史上に突然現れた傑作ではなく、それ以前に書かれた古典に多く由来している。老子・荘子、四書五経、論語、枕草子、万葉集、そして方丈記(徒然草の約100年前に書かれた)についてもばっちり引用している。「もののあはれ」や「無常」という価値観・美意識は、こうして代々日本人に受け継がれてきたようだ。
- 万事に、あまり立ち入らないのがよい(79段)
- しようかせずにおこうかと思うことは、たいがいしないほうがいいのである(98段)
- 改めても益のないことは、改めないのがよいのである(127段)
こういう発想が、いかにも東洋の古典らしい。「道は常に無為にして、而も為さざる無し(老子37章)」をまさに地で行く感じといえるし、家の設えや趣味については「無作為」という価値観(231段)が徹底している。
Time is money?
「常住ならぬ転変の現生(91段)」、無常(死)はすぐにやってくるという基本認識のもと、仏道でも世俗の仕事でも、何かひとつやると決めたら他のことは無視して修行に励もう、としつこく説教している。59、108、155、188段はすべて「光陰矢の如し、少年老い易く学成り難し」といった感じの内容だ。
鎌倉時代の平均寿命は24歳だったらしいので、「何をやるにも時間が足りない」という事情は今より切実だったのだろう。当時はちょっとした病気や栄養失調であっけなく人が死ぬ時代だった。吉田兼好自身はそれなりに身分もあり(いい暮らしをして)、70歳近くまで生きたようである。
「せいぜい四十に足らぬほどで死ぬのがころ合いでもあろうか(7段)」と言っているが、長生きしたために著作を後世に残せたともいえる。武士道とは死ぬこと…『葉隠』の著者、山本常朝が意外と長生きした(60歳)のと似ていて、生存バイアスとでもいえる現象だ。
時間が大事とは言いつつも、別のところでは「幻のような人生において、成就するに足る何事があろうぞ。いっさい欲望はみな妄想である(241段)」と語られる。時間管理や仕事術的なエピソードを交えつつも、本来あくせく働くのは馬鹿らしい(74段)と考えているようだ。
そのベースには、人の命は常住不断(7段)なので(欲望を捨てる修行以外)何をやっても一切無駄という諦念がある。無常という真理の前では、主君への忠義や親孝行という武士道的な価値観でさえも否定される(59段)。
金持ちでも貧乏でも違わない
経済的な面に関しては一貫して「人間の欲望はきりがないから、財産を蓄えるより持たない方がまし」というポリシーだ。特に217段は、ある大富豪の語る倹約と蓄財に関する逸話を紹介しつつ(一般的には見習うべき教訓)、以下のように価値観をひっくり返している。
富の欲を満たして楽とするよりも、むしろ財産のない方がましである。 癰疽(ようそ)を病む者が患部を水で洗って楽しいとするのよりも、病気にかからぬがいっそうよかろう。(217段)
お金を貯めることを目指すより、お金がなくても気にしない方が幸せだというのである。著者は質素な暮らしをしつつも苦労して働いているようには見えないから、年金か印税か資産運用で暮らしているのだろう。おそらくは「食うに困らない程度に財産があればよい」という意味である。
そして217段がその後、「貧富の区別もなく、凡夫も大悟徹底の人も同等で、大欲は無欲に類似している」と続くのは重要な部分だ。金持ち/貧乏がよい、という議論を越えて、どちらでも構わない(どうせ無常なのだから)というのである。
善悪を越えた価値観
『徒然草』の著者が表明する価値観とは、最終的に聖俗二元論を越えたところにある。まさに「心の欲する所に従えども矩を踰えず」という自由闊達、天衣無縫な境地について語られている。
真人は知もなく、徳もなく、功名もなく、名誉もない。だれがこれを理解し、これを世に伝えようや。べつに徳を隠し、愚を守るというわけでもない。本来が賢愚得失の境地には住んでいないのだからである。(38段)
もしこれが単なる隠遁者の厭世観をつづっただけの陰気な書物だったら、B級品として(歴史的な価値はあるが)ここまで広く読まれなかっただろう。特に輪廻転生とか解脱というような仏教的理想については説明されていないが、まるで禅僧の本を読んでいるようなすがすがしさに満ちている。
たとえば「義理も礼儀も忘れて構わない(112段)」という隠者らしい過激な発言が、『徒然草』の本当の魅力でないかと思う。妻や子どもはいらない(6段、72段、190段)とか、女性嫌いな側面(107段)もうかがえる。このあたりの偏った思想が教科書で取り上げられることはまずなさそうだ。
世捨て人らしい自由な発言
ユーモアにあふれた逆説を通して、特定の価値観への執着をあざ笑うのが著者の個性といえる。その嫌みな性格が端的に表れているのが以下の部分。
その物に付着して、その物を毒するものが無数にある。たとえば、人体に虱、家に鼠、国に盗、小人に財、君子に仁義、僧に法など。(97段)
そして日記を書きながら気分にむらがあるのも、人間らしい一面といえる。中にはめずらしく、酔っぱらって書いたのではないかと思われるような(兼好は酒飲みが嫌いだが酒は嫌いでない)、感情的な一文もある。
約束も守るまい。礼儀をも気にかけまい。この心もちを感じない人は、われを狂人と言うならば言え、放心者、冷血漢など、なんとなりと思え。そしられたって苦にはしない。(112段)
日本一有名な世捨て人の面目躍如だ。現役時代は和歌四天王と呼ばれたプロの著述家が、引退して気晴らしにのびのび書いている印象を受ける。
本当は人に見られたくなかった書き物だったようだが、結局残ってしかも三大随筆に祭り上げられてしまったのは皮肉である。作家としての性には逆らえなかったのだろう。
残されるはずでなかった書物
実はこの作品について「つまらぬ遊びごとで破き捨てるつもり(19段)」と宣言している。「死後には残しておきたくないような古反古などを破り捨て…(29段)」とあるが、『徒然草』はなぜか生き延びた。
途中で気が変わったのか、処分する暇もなく往生してしまったのか、焼き捨てるという遺言が果たされなかったのか、真相はさだかでない。そもそも吉田兼好が単一の作者なのか、後の時代にどの程度修正が加えられたのかも疑わしい。
著者の思想からすると、死後の名声など興味なかったはずだし(38段)、そもそも文芸活動ですら余計とみなしているふしがある。信条どおりに、何も書き残さずひっそり去っていった沈黙の隠者は他にごまんといることだろう。
死後の毀誉褒貶はどうでもよいとすると、恥ずかしい日記が人に見られても構わないということになる。実は適当に書き散らした年寄りの愚痴と見せかけて、慎重に構成を組み立てた労作だったのかもしれない。本筋から外れた伝聞メモも、故意に挿入された撹乱工作もしくは暗号なのだろうか。
あるいは深読みするだけ無駄で、本当につれづれ書いていただけの備忘録だった可能性もある。単に「古い」という理由でありがたがられているだけだったら、平城宮跡から発掘される落書き木簡と変わらない。
いずれにしても、著者自身がこれを楽しんで書いていたといのは間違いない。一部に矛盾もあり、多義的で人によっていろいろな読み方ができるというのが、徒然草の魅力なのだろう。
センスのいい雑記ブログを眺めるように楽しく読めたのは、佐藤春夫の名訳による部分も大きい。原文は収録されていないが、河出文庫の現代語訳はコンパクトで持ち運びにもおすすめだ。