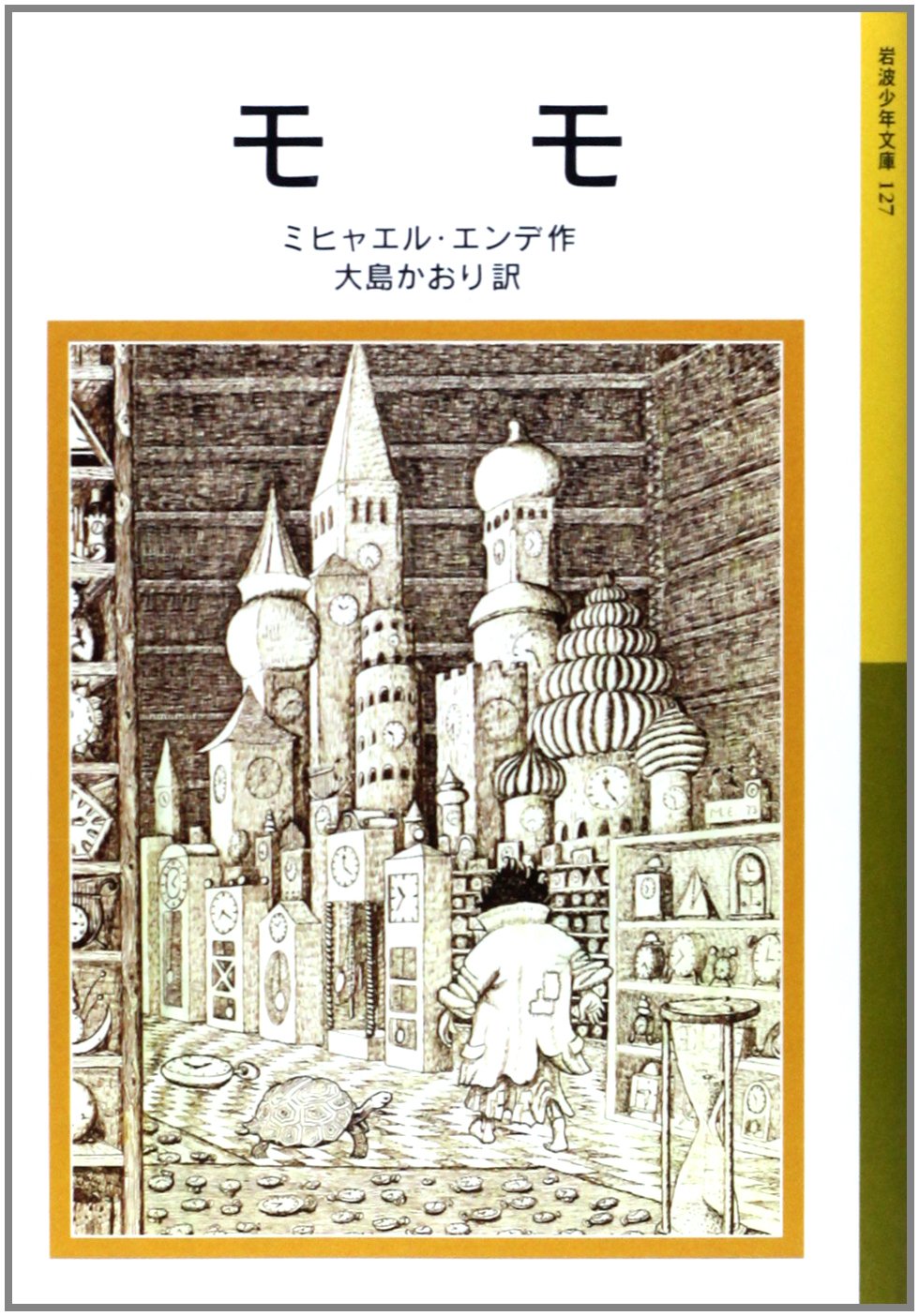児童文学としては、『星の王子さま』と同じくらい有名に思われるミヒャエル・エンデの『モモ』を読んでみた。子どもの頃は知らなかったが、むしろ大人の方によく読まれている作品に思われる。ビジネス書や、スローライフ・ロハス的な本でもたびたび引用される。
ちょっとした絵本くらいに思っていたら、岩波少年文庫の翻訳でも400ページくらいある。対象は「小学生5・6年以上」で、勧善懲悪でない含蓄の深い話も多い。主人公モモと時間どろぼうの戦い、時間の国を行き来する冒険譚でさくさく読めるので、週末1日あれば読破できるくらいだ。
章ごとに含まれる挿絵は、エンデ自身が描いたものらしい。文字が日本語になっているので不思議なのだが、奥さんが日本人でたびたび日本にも来ていたようなので、言語に堪能だったのかもしれない。
主人公のモモは小汚い浮浪少女
表紙の時計が並んでいる部屋の絵がいちばん緻密で、『モモ』のイメージとして定着している。この絵の中央、後ろを向いて歩いている髪を逆立てたマッドサイエンティスト的な人影が、最初はマイスター・ホラかと思ったのだが、どうやらモモ本人であるようだ。
主人公モモは、郊外の円形劇場に住み着いた浮浪児の女の子という設定なっている。場所はヨーロッパでもイタリアとか南の温暖な気候を想像させる。村人が、身寄りのないモモを警察に届けた方がいいじゃないかとか相談したり、モモが施設から逃げてきたとか、わりと現実的な話から始まる。時代設定としてはこの作品が書かれた1973年と同じ、20世紀の話でないかと思う。
モモには「人の話をよく聞ける(話を聞いてもらうとその人の気持ちがすっきりする)」という傾聴の特技がある。このため、働かなくてもまわりが食べ物を持ってきてくれたり、村人とは協調的な関係を築けている。見た目はきっと表紙の絵のように、小汚くて臭そうな不良少女だったと思う。しかしその非常識さゆえに、後に登場する時間どろぼうたちにとってはモモの存在が脅威になるのだ。
エージェント・スミスの元ネタ?
この作品のユニークな点を一つ挙げるとすれば、敵役の時間どろぼうが憎めない、いやむしろ正論を吐いているように思われることだ。結局彼らは人間でなく、モモの活躍によって最後の一人まで消滅させられてしまうのだが、そこは児童文学としての設定だったのかもしれない。
映画『マトリックス』のエージェント・スミスは『モモ』の「灰色の男たち」からインスパイアされたように思う。無限に湧いてきて物量で攻めてくる不気味さはそっくりだ。
節約して時間銀行に預けた時間が、結局その人には戻ってこないという詐欺が行われているので、最終的に彼らは悪だと腑に落ちる。その点を除けば、むしろ怠惰より勤勉を奨励するまともな考え方、プロテスタンティズムの倫理とでもいうべき両義的な意味をになっている。
最後に残った灰色の男が消える際、「いいんだ―これでいいんだ―なにもかも―おわった―」と言い残すセリフが興味深い。すなわち、人間の意思から生み出された「時間節約」の化身である灰色の男たちも、実は自身の存在や役割がいやになっていたのではないか。
おとなは、子どもがいやになったんだ。でも、おとなじしんのこともいやになってる。なにもかもいやになってる。これがおれの意見さ。
ミヒャエル・エンデ 『モモ』 大島かおり 訳
フランコ少年のいうとおり、倹約という手段が目的化してしまった大人も時間どろぼうも、実はそんな習慣が内心いやでたまらないのだ。そういう機械的・画一的な生活が、人間の本性に生理的に反していることは、うすうす気づいているのだろう。
行き過ぎた倹約をやめたいけれども、習慣化してしまってそれ以外のやり方や考え方を思い出せない…なんとなく『星の王子さま』に出てくる酒飲みの大人たちの惑星を思い出させる。
目的のない倹約の愚
「人間が時間を節約すればするほど、生活はやせほそっていく」…とはいえ、会社で仕事中にマイペースで散歩したり昼寝しはじめたら、気が狂ったと思われるのがオチだろう。
単に節約が悪なのではなく、「何のために時間を使うか」ということが問題とされている。その上で灰色の紳士が掲げるスローガンが、ことさら間違っているように聞こえないところが問題の本質といえる。
「人生でだいじなことはひとつしかない。」男はつづけました。「それは、なにかに成功すること、ひとかどのものになること、たくさんのものを手に入れることだ。ほかの人より成功し、えらくなり、金持ちになった人間には、そのほかのもの―友情だの、愛だの、名誉だの、そんなものはなにもかも、ひとりでにあつまってくるものだ。」
ミヒャエル・エンデ 『モモ』 大島かおり 訳
立身出世の美徳というのは、日本でも階級意識が薄れた明治期以降、世間の常識(あるいは宗教・倫理)として定着しているように思う。時間どろぼうと取引せず、モモのように呆けて暮らせば、ドロップアウトした負け犬のような後ろめたい気持ちで暮らすことになるだろう。
少々長いが引用すると、床屋のフージー氏のセリフは現代人の基本的な考え方と当惑を端的に表しているように思う。
「おれは人生をあやまった。」フージー氏は考えました。「おれはなにものになれた?たかがけちな床屋じゃないか。おれだって、もしもちゃんとしたくらしができてたら、いまとはぜんぜんちがう人間になっていたろうになあ!」
でも、このちゃんとしたくらしというのがどういうものかは、フージー氏にははっきりしていませんでした。なんとなくりっぱそうな生活、ぜいたくな生活、たとえば週刊誌にのっているようなしゃれた生活、そういうものをばくぜんと思いえがいていたにすぎません。
ミヒャエル・エンデ 『モモ』 大島かおり 訳
目的がはっきりしないまま現状に不満を抱えて過ごすことがナンセンス、と著者のエンデは言っているように見える。
理想化された道路掃除夫の労働観
一方、モモの暮らしは特殊すぎるので、大人が目指すべき理想的な生き方・働き方として描かれているのは、時間どろぼうに支配される前の道路掃除夫ベッポと観光ガイド・ジジだろう。
ベッポの職業はさえない掃除夫なのだが、本人はいたって満足して丁寧に仕事をするよう心掛けている。目の前のタスクだけを考えるという、まるで禅僧のような労働観がよしとされている。
いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな?つぎの一歩のことだけ、つぎのひと呼吸のことだけ、つぎのひと掃きのことだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。
ミヒャエル・エンデ 『モモ』 大島かおり 訳
ベッポが灰色の男たちにだまされて、時間を節約するためだけに手早く仕事をするようになると、堕落したように描かれている。効率は上がるかもしれないが仕上げは雑で、そういう心のこもらない働き方では、ベッポ自身の気持ちもすさんでくる。さらに失踪したモモを探そうとして警察に拘留され、精神病院にまで入れられてしまう。
行き過ぎた合理化の非合理性
著者の主張としては、「結局身の丈にあった今の仕事をまっとうするのが肝要で、下手に転職するとか荒稼ぎするとか、欲を出さない方が身のためだ」と解釈できる。
時間どろぼうのおかげでジローラモも有名人になり、客観的には成功したように見えるが、内心は落ち着く暇がなく不幸に感じている。マイペースで無理なく続けられて、個別のお客さんの満足を第一に考えられるような働き方が尊い、そういう思想に思われる。
町外れで小さい居酒屋をやっていたニノが、時間どろぼうとの取引後にファストフードレストランを開業しているのは滑稽な一幕だ。モモはレジ係のニノと話をするために、何度も食事をして列に並ばなければいけない。長い通勤時間、休日の道路渋滞…ついつい慣れてしまいがちな現代的な風景も、合理化を突き詰めたら出てきた非合理性なのだろう。
時間の倹約も貯蓄と同じで、別に本人が好きでやっているならどうでもいいんじゃないかと思う。満足して暮らしても、欲求不満で暮らしても、結局飯を食って寝て死ぬだけの人生だ。
左官屋の二コラや床屋のフージー氏のように、将来はなにかもっとましな暮らしができるとか、今の暮らしが間違っているとか、そういうありもしない妄想を生み出してしまうのが人間の性ともいえる。
大人の不思議な行動を、子どもの目線でユーモラスに描き出したのが『モモ』の魅力なのだろう。